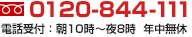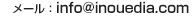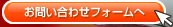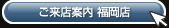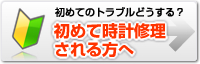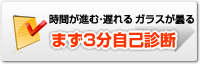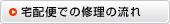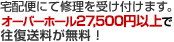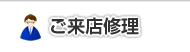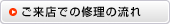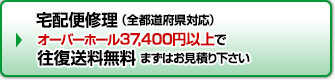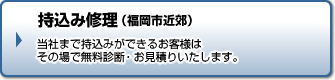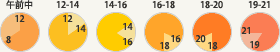用語集【ま~わ】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイクロ・ガスライト安全性に配慮された密封ガラス・チューブにトリチウムガスを封印。ガラス内でトリチウム電子が光を放つことで輝度を得る自発性の夜光システム。従来の夜光の約70倍の明るさを10年間以上も保ち続ける、優れた特性を持っている。 マイクログラフ3秒で1回転するストップウォッチ秒針を持ち、1秒の1/100分割計測ができるストップウォッチのこと。1916年にタグホイヤーの前身であるホイヤー社が開発した。6秒で1回転することによって、1秒の1/50分割計算ができるセミクロノグラフもある。 マイクロータームーブメントの中心からずれた位置に回転軸がある自動巻ローターのこと。そのため回転軸がムーブメントの中心にあるタイプに比べ薄くできる。ユニバーサルのホワイトシャドウがマイクローターを搭載し、一世を風靡した。マイクロ(小さな)ローターを略してマイクローターと名付けられた。 巻真リュウズ、キチ車、ツヅミ車が付いたゼンマイを巻いたり時刻を合わせたりするための軸のこと。巻真の先端に付いたリュウズを引っぱることによって、ツヅミ車がキチ車から離れ小鉄車と噛み合い時刻を調整できる。 マニファクチュールムーブメント専門メーカーが製造したムーブメントを使わずに、ムーブメントからケース、ベルトに至るまで全ての部品を自社で一貫して製造し、組み立てる技術を持った時計メーカーのこと。主なコンプリートメーカーはパテック・フィリップ、IWC、ゼニス、バシュロン・コンスタンチン、オーデマ・ピゲ、ロレックス、ジャガールクルト、ミネルバ、ランゲ&ゾーネ、ジラール・ペルゴなどの高級時計メーカー。 マリンクロノメーター船の上で普通の時計を使うと、揺れなどによって正確に計ることができない。そこで、海上でも高精度を保てるように作られたのがマリンクロノメーターで、ジンバル(据え付け式)によって文字盤が常に上を向く構造にになっている。イギリスの時計技術者ジョン・ハリソンによって製作されたものが史上初。 丸穴車巻き上げ機構パーツのひとつで、キチ車と噛み合っている。リュウズからツヅミ車、キチ車と伝えられた動力を角穴車に伝える役割をする。 マルチバンド周波数を切り替えることで、日本の他、アメリカやドイツ、中国など他国でも標準時刻電波の受信が可能な電波時計。 万年時計文字通り万年カレンダーを搭載した時計のこと。例えば文字盤にある西暦年表示を知りたい月に合わせると、その曜日が表示される。その日が何曜日なのかいつでも知ることができる。 水時計太陽がでていない時や夜に時刻を知ることができない日時計に代わり、考案されたのが水時計で、瓶に溜めた水を滴り流していき、瓶に刻んだ目盛を読むことによって時刻を知っていた。 3つ目モデルクロノグラフ機構を搭載したモデルのうち、30分&12時間積算計、スモールセコンドの合計3つのインダイアルを装備したモデル。 ミニッツカウンタークロノグラフにおける分積計算カウンターのこと。クロノグラフ秒針と連動していて、60秒経過するとミニッツカウンターが1目盛進む。30分に1回転する30分計が多い。 ミニッツリピーター複雑機構の中でも最も高度な技術を要するもので、ボタンやレバーを作動させることによって音で時刻を知らせる機能。2種類のハンマーとゴングが内蔵されており、低音と高音、和音の3種類で時刻を知らせる。時間を知らせる低音の鐘が3回鳴ったら3時、15分単位を知らせる和音が2回なら30分、そして1分単位を知らせる高音が鳴ったら5分、つまり、3時35分となる。暗闇などの文字盤が見えない状態でも時刻を知ることができる。 ミニッツレコーディングホイールミニッツカウンターと同軸にあり、クロノグラフランナーが1回転すると中間車を介して動力が伝えられる。30分で1回転する。 ミネラルガラス無機ガラスと呼ばれる普通のガラスのこと。強度は低く、カット面を太陽光に照らして横から見ると青く見えるのが特徴。 ミルスペック軍隊に制式採用されるための品質規格。視認性や機能、制度、文字盤カラーやインデックス、防水性など、各国の陸・海・空軍別や舞台ごとに、その目的や使用状況に応じ細かく定められている。 無反射コーティングガラス表面に、フッ化マグネシウムを真空蒸着するなど特殊なコーティングを施して光の反射を抑え、視認性を高めたガラスのこと。コーティングされる薄い皮膜は多層構造と単層構造に分類でき、またコーティング処理もガラスの片面と両面に施される場合があり、モデルの用途や種類によって使い分けられている。 ムーブメント時計を動かす機械のことで、動力源となるゼンマイが納められた香箱車、香箱の動力を伝える輪列、規則正しく輪列を動かすための脱進調速機構などから構成される。その他、自動巻ムーブメントにはローターが加わり、クロノグラフにはクロノグラフ機構が加わる。 ムーンフェイズ文字盤にある月齢表によって月の満ち欠けを知ることができる機構。月の満ち欠けの周期は29.5日なので、月が書かれたプレートは29.5日で半回転する。扇形の小窓から見える月の形によって、一目で三日月、半月、満月などを知ることができる。月齢とも言う。 メッキ電気分解をすることによって金属の薄い膜を密着させること。金メッキでは厚さ1ミクロン前後の膜を使用する。金張りは方法が異なる。メッキと言っても5ミクロン程度なので厚いからといって金張りというわけではない。最近では10ミクロンくらいのものもあるが、通常は50から100ミクロンくらい。 メテオダイアル地球に落下した隕石(メテオライト)を素材にしたダイアル。希少価値が高く、独特な質感を持つことで人気が高い。 メメントダイヤル時計の計測とは無関係のインダイヤルで、時刻を記録するための機能。 メロディ運針正時などの一定時刻や操作することによってメロディがなり、そのメロディに合わせて針も運針するという機能。 面取り加工部品の角や縁を、滑らかに研磨加工すること。これを行なわないと部品同士の摩擦が大きくなったり、部品自体が金属疲労で破損しやすくなり、時計の寿命も短くなるといわれている。 文字盤ダイヤルの項参照 モジュールもともとは、パソコンなど電子工学&プログラミング業界の「交換可能な、まとまりのある部品=機能性を有した構成要素の集合体」を指す用語のこと。時計業界では「交換や増幅可能な(機能を持った)機械ユニット」を指す言葉として使用され、たとえば「自動巻きムーブにクロノグラフモジュールを追加」などと使われている。 モース硬度宝石などの鉱物の硬度を表す尺度。ガラスは7で、ダイヤモンドが最高のモース硬度10となる。硬さの絶対値ではなく順番のこと。絶対値はヴィッカース硬度。 モバードグループクロノグラフやトリプルカレンダーの自社ムーブ開発などで知られたスイスの名門モバードと、エベル、コンコルドで構成される時計ブランド集合体。 夜光塗料暗い場所でも時刻を確認できるように、針やインデックスを光らせることができる塗料。光を吸収・蓄積して発光するN夜光と、ラジウムやトリチウムなどの光を吸収しなくても自ら発光する自発光型塗料とがある。 遊革ベルトを締めたときに剣先の余った部分を留めるためのパーツ。ベルト上を自由に移動することができるリングのことを遊革、ベルトに固定されているリングのことを定皮と言う。 UTCUniversal Time Coordinatedの略で協定世界時のこと。協定世界時の項参照。 ユニークダイアルロレックスのアンティークモデルなどに見られる、上半分のインデックスがローマ数字、下半分がアラビア数字になったダイアルデザインのこと。 ヨッティングクロノグラフその名の通り、ヨットレース専用に作られたクロノグラフ。スタートまでのカウントダウンが一目でわかるように、5分刻みで色分けされた分積計算ダイヤル(ヨットダイヤル)が付いている。 4番カナ4番車の真軸まわりに付いた歯車で、3番車から伝わった動力を受けて4番車を回転させる働きをする。 4番車3番車とガンギ車の間にある歯車で、カンギカナと噛み合っている。60秒で1回転する。スモールセコンド付時計の場合、スモールセコンドの秒針と同軸になる。 4分の3プレート裏ブタを開けた際のムーブメントの装飾性を高めるため、ツヤ消し加工や模様が描かれた大きな受け板で、全体の75%以上を覆ってしまう技法。ドイツ時計産業の中心地であるグラスヒュッテで、古くから採用されている。 ライダータブブライトリング社の「クロノマット」や「アベンジャー」シリーズなどの回転ベゼルに装備される小さな突起状部品。手袋をしたままでもベゼルを操作しやすくし、さらに風防ガラスを過酷なGなどの衝撃から守るクッションの役目も果たしている。 ラウンドケース丸型形状の時計ケース。 ラグケースとベルトを連結するケース部分のこと。 ラジウムキュリー夫妻が1898年に発見した放射性物質で、ラジウムをもとにパネライが蛍光体ラジオミールという夜光塗料を開発した。ダイバーズウォッチの針やインデックスに使われていたが、安全上の理由から現在ではトリチウムが使われている。 ラック&ピニオン溝が刻まれたレールの上を、車輪状の歯車が回転しながら進む方式のこと(山岳鉄道などに見られる移動方式)。回転計算尺や回転式のインナーリング、ベゼル類は、通常の構造だと操作時などにズレが生じることもあるため、歯車が溝にひとつずつに噛み合うこの方式にすることで、ズレの発生などを防止している。 ラップタイム中間地点から次の中間地点までにかかる経過時間、すなわち途中計時のこと。例えば長距離走などでトラックを10周する内の1周ごとのタイムを言う。 ラトラパンチスプリットセコンド(ラップタイム)機構を搭載したクロノグラフ。フランス語で、「追いつく」という意味の言葉が語源となっている。 リシュモングループカルティエを中心として、時計や宝飾、服飾分野を多彩に展開する高級ブランドグループ。パネライやIWC、ヴァシュロン・コンスタンタン、ジャガー・ルクルト、ボーム&メルシエなど多くの著名時計ブランドがこれに所属。1991年からはバーゼルフェアを離れて独自の新作時計発表会「ジュネーブサロン=SIHH」を毎年、定期開催している。 リストウォッチ腕時計の項参照 リダン日焼けなどで変色したりヒビが入ってしまった文字盤を書き換えること。古い塗装を剥がして文字盤に再塗装するので美しくなるが、オリジナリティは失われる。 リバースカレンダー一般的な小窓の数字が変わることによって日付を知らせるカレンダー機能とは違い、扇形状に表示するカレンダーにおいて月末が来ると、または操作によって瞬時に針が戻る機能のこと。 リピーター音を鳴らして時刻を知らせる機能、時計の総称。指針が示した時刻を再び音で知らせる(報時を服する時計)ということからリピーターと呼ばれる。時単位、15分単位、1分単位の3種類の音を鳴らすミニッツリピーター、時単位、15分単位、5分単位の3種類の音を鳴らすファイブミニッツリピーターなどがある。1676年にエドワード・バーローが発明したと言われている。 リファレンスナンバー裏蓋などにRef.の次に表記されている番号で、このナンバーによりデザインを識別することができる。 リュウズ巻真の先端に付属していて、ゼンマイの巻き上げや時刻調整を行なうために必要なパーツ。丸型、角型、平型、ファセット型などの形があり、ダイバーズウォッチなどで使われているリュウズはねじ込み式のスクリューロックリュウズと言われるものが使われており、防水性に優れた仕組みとなっている。高級時計にはそのメーカーのロゴが刻印されたものが多い。 リュウズガード外部からの衝撃からリュウズを守るために、リュウズの周りに設けられたガードのこと。上下に付くタイプが主流だが、セクターのようにフルカバータイプもある。 輪列歯車やカナから構成された香箱車や1番車、2番車が噛み合うことにより動力を伝達する機構のこと。香箱から4番車までを表輪列と言い、ツツ車、日の輪など文字盤側の歯車を裏輪列という。 ルノー・エ・パピ天才時計師と謳われたジウリオ・パピと、ドミニク・ルノーによって1986年スイス・ジュウ渓谷のル・ロックルに設立されたムーブ製造メーカー(1992年にオーデマ ピゲの子会社に)。トゥールビヨンやミニッツ・リピーターなど、ハイコンプリケーションを開発&製造できるスイスでも数少ない技術を持つ名門メーカーとして名高い。 レギュレーター「時」「分」「秒」を正解に認識&判別するため、時・分・秒針をそれぞれ独立させて設置した時計。もともとは時計メーカーや技術者、科学者などが、製品や科学データのチェック用に使用していた高精度クロックの名称。 レクタンギュラー縦に細長い、長方形の時計ケース。 レーシングウォッチタキメーターやスプリットセコンドクロノグラフを搭載し、カーレースに対応する時計のこと。 レトログラード(フライバック)針が1周しないで扇形を描き、目盛の端まで来ると瞬時に開始時点に戻る機構。ジラール・ペルゴ、ジャガー・ルクルト、ピアジェ、ゼニスなどの高級時計に見られる。 レマニア1884年にロリエントに設立されたムーブメント会社。1910年代にオメガのムーブメントを製造し始めた。1932年にはオメガを中心としたSSHIグループの傘下となった。クロノグラフ懐中時計のムーブメントや初期モデルのスピードマスターに搭載されたキャリバー321などの開発にも関わっている。 レールウェイ鉄道線路をモチーフにして、ダイアルの外周部などに四角くデザインされた二重線ライン。 ロゴダイアルに描かれた、メーカー名や製品(モデル)名マークのこと(LOGOTYPE=ロゴタイプの略称)。 ローター自動巻ムーブメント機構でゼンマイを巻き上げ、エネルギーを蓄えるための両方向回転式の重り。材質は真鍮が一般的だが、金なども使われることがある。 ローティングインジケーターシステム通常はインダイアルに針で表示されるクロノグラフの積算分やスモールセコンド(秒)を、回転するディスク盤で表示する方式。 ローテーションセーフティシステム回転ベゼルの誤作動や誤操作を帽子するため、ベゼルを一段上へ引き上げないと回せないようにした安全装置のこと。 ロービートテンプの振動数が、毎秒6回(毎時2万1600振動)以下に設計されたムーブメント。やや重量のある大型テンプをゆっくりと回転させるタイプで、1940~50年代頃までは主流となっていた。ガンギ車の歯数もハイビートタイプより少なく、またアンクルも大型なため(ハイビートタイプは逆に歯数の細かいガンギ車と、小型のアンクルを採用している)、注油や組み立てなどの調整作業は比較的容易。メンテナンス性や耐久性にも優れた特性を持っている。 ローマンインデックスⅠⅡⅢとローマ数字で表示されるインデックスのことで、時計がクラシカルな雰囲気になる。 和時計季節によって一刻(現在の約30分間)の時間を変えるという不定時法があった昔の日本において、その時刻制度に対応できるように作られた日本独自の時計。明治5年に西洋から制度の高い時計が大量に輸入されたため、次第に衰退していった。 ワールドウォッチ文字盤やベゼルに世界主要都市の標準時が記載されていて、時差計算をしないでも任意の2ヶ国の時間がわかる時計のこと。 ワールドギャランティーカード時計メーカーが発行する国際品質保証書。新品の販売時に限り1枚1回だけ発行される。 ワールドタイマー回転ベゼルやインナーリングを操作すれば、ダイアル外周部などに時差別に刻まれたその他の世界主要国(都市)の現在時も、同時に知ることができる機能を備えた時計。 ワンピースケース通用の時計外装部品はケース本体とガラス、裏ブタの3ピースで構成されているが、防水性を確保するためなどの理由で、裏ブタとケースを特に一体構造(削り出した金属の塊)にしたケースのこと。 ワンプッシュクロノグラフプッシュボタンが一つのクロノグラフ。通常2つのプッシュボタンをリュウズに納めたモデルやリュウズ自体がプッシュボタンを兼ねたモデルもある。積算はできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用語集【あ~お】 |
ISO規格国際標準化機構(International Lrganization for Standardization)が定めた規格。国際交流を容易にし、活動を円滑にするために製品やサービスの用語や単位などの世界的な標準化を目的として定められた。時計では、耐衝撃、一般防水、潜水用腕時計などが定められていて、ダイバーズウォッチとそのほかの時計を区別するために表示される。 アガキ歯車と歯車の間や香箱と香箱真、受け石と歯車の軸などの接点に設けられた隙間のことをいう。アガキがないとスムーズに動かすことができない。 アカデミー「スイス伝統の時計製造技術」の継承と、会員間の情報収集&協力を目的に、スヴェン・アンデルセン、アントワーヌ・プレジウソ、フィリップ・デュフォーらを中心メンバーに1984年、スイス・ジュネーブに創設された独立時計師たちの会員組織。正式名所は「Horological Academy of Independent Creators(略称=A.H.C.I.)」その活動は多岐に渡り、バーゼルワールドでの新作展示発表(毎年専用ブウースで行われている)や、HPでの作品&作者紹介、若手時計師の育成活動などを軸に展開している。 足ブレスレットや皮のベルトなどを取り付けるための出っ張り部分のこと。バーやリング状のものや、先が細くなったツノ状のものなど形は様々。ラグやカンとも呼ばれる。 アジャストスクリューネジムーブメントを構成する極小ネジのひとつで、天輪に装着されている。精度を微調整する働きがある。同じ天輪に装着されているチラネジは、テンプ自体のバランスをとるものなので働きが異なる。 アシンメトリック左右が非対称にデザインされた時計ケースやダイアルデザインのこと。左右のボリュームや配置にあをつけることで、装飾性とインパクトを高めている。主にドレス系モデルに採用される。 アズモメータークロノグラフに設けられた呼吸数を計測するための機能。1回目の呼吸をしたらスタートボタンを押し、15回または25回目の呼吸を終えたらストップボタンを押す。その時に指す目盛りの数が1分間の呼吸数となる。主にドクターウォッチに使用される。 アップライトインデックスダイヤル(文字盤)から立体的に浮き出ているインデックス(時刻を表すマーク)のことを言う。文字盤の裏からプレスして凸面が作られたプレス型と文字盤に穴を開け、差し込んで固定する植字型とがある。最近は安価な接着式が多くなっている。 アナデジウォッチ時計や分針、秒針など針でメインの時刻表示を行なう他、クロノグラフ計測値(100分の1秒や1000分の1秒)、カレンダーなどの情報をもデジタル小窓で表示するクオーツ時計のこと。 アナログウォッチ針の動きで、時・分・秒などのメイン時刻を常時する方式の時計。一般的な長・短針を備えた時計の総称(針の動きが連続性のある流れるような動き=アナログであるのがその語源)。 アニュアルカレンダー永久カレンダー機構の一種。1年に一度、2月の末日にだけ手動操作で日付けの早送り調整が必要だが、その他の月は日付けを自動的に正しく表示する機構(パーベチュアルカレンダー参照)。 アビエーションウォッチベゼルに付いている回転計算尺で、速度やガソリン量を割り出せる航空時計のこと。世界初の太平洋無事着陸横断を成功させた探険家チャールズ・A・リンドバーグが、1932年にロンジンとともに開発したアワーアングルウォッチが史上初のモデル。 油金属パーツを傷めないようにし、パーツ同士を滑らかに動かすための潤滑剤のこと。細やかな部品が働きあっているムーブメントには、薄くて強力な油膜を張ることができる油が必要とされる。油がきれると鉄粉などが溜まり、動きに支障をきたしてしまう。 アブライドインデックス時を示す数値やマーク(時字=「ときじ」とも呼ばれる)を文字盤に貼り付けたタイプのインデックス。くさび状の金属部品を文字盤から裏側へ爪で喰いこませるように設置する高級仕様と、単に接着加工する簡易型仕様がある。 アミダ歯車の横の棒のことで、車輪でいうスポークの役割をする部分。アミダが曲がってしまうと姿勢が変わってしまい、誤差が発生してします。初期は2本のものが多く、後に3本や4本のタイプが出てきた。 アモータイザーケースバックに設置されたプロペラ状の部品を回すと、自動巻きのローターがロックされ、落下などのショックが加わった際の(ローターの激しい動きによる)ムーブの損傷を防止するための装置。バール ウォッチが開発したオリジナル機構。 アラーム設定した時刻に音を鳴らして知らせる機能。設定時刻を解除しない限り1日1回鳴るデイリーアラーム、設定した時間にアラームが一度鳴ると自動的に設定が解除されるワンショットアラーム、複数の時刻が設定できるマルチアラームなどがある。史上初のアラーム付きウォッチは1947年に発売されたバルカンのクリケットである。 アラームウォッチあらかじめ設定された時刻になると、ケース内部に設置されたアラーム用のハンマーが金属塊やリング部品を叩いてベルの鳴る機構を搭載した時計。 アラビックアラビア数字のこと。1,2,・・・で表す算用数字で、アラビックインデックスとはアラビア数字を数字体としたインデックスのことを言う。アラビックインデックスは、スポーツ時計やカジュアル時計に用いられることが多い。メーカーによっては書体を変えて使っているところも多い。 アワーアングルウォッチチャールズ・A・リンドバーグが1932年にロンジンと開発した航空用の時計。世界で初めて大西洋単独横断無事着飛行に成功したリンドバーグは、経度が計算できる航空用の計器を考案し、それを元に作られた。 アワーマーカー時を示すための文字盤上の目盛のこと。インデックスとも言う。文字盤から浮き出したアップライト式と文字盤に直接プリントされたプリント式とがある。 アワーレコーディングストップウォッチ機能が付いた時計をクロノグラフと言い、その中でも12時間計が搭載されたものをアワーレコーディングと言う。30分刻みのものと1時間刻みの2種類がある。 アワーレコーディングランナークロノグラフ機構に置いて12時間計を動かすための歯車。時計によってはこの歯車が無いタイプもある。 アワーレジスタークロノグラフなどの文字盤内に、計測開始からの経過時間を1時間単位で表示するために設置された小さなダイアル。12時間まで計測できるタイプが多く、その場合は「12時間計」と呼ばれている。 アンクルテンプとカンギ車との間にある脱進機を構成する部品のひとつで、2つのツメ石を持ち、錨型をしていることからこう呼ばれる。入りヅメ、出ヅメの2つのツメ石がカンギ車を交互に進め、テンプの振動を調整する。このアンクルを持つ脱新機構をアンクル脱進機と言い、アンクルの軸を支えておく受け板のことをアンクル受けと言う。規則正しい輪列運動をするためには欠かせないパーツのひとつである。 アンチショックテンプの芯を受ける、軸受け部分に過巻状のバネ(ショックアブソーバー)や特殊な枠部品を装備することで、衝撃時にテンプの軸が受け板からズレたりはずれたりしない構造にした、時計の耐衝撃機構のこと。 アンチマグネチック金属部品で構成された時計のムーブメントが、磁気を帯びてしまうことを防ぐため(部品が磁気を帯びると等時性が損なわれ、精度悪化などを招く)、二重構造ケースやリング状部品、シールド材などで保護された構造を持つ時計やその機構。 イオンプレーティング高真空下でイオン化(カス化)した金属微粒子を飛ばし、素材となる金属に衝突させながらその金属の表面に頑強な薄い皮膜を作るコーティング技術。時計の場合は装飾性と堅牢性を高めるためケースやブレスに主に使用され、IP加工と略されて表記されることが多い。一般的には窒化チタンをガス状にしてコーティングすることが多く、ガスの成分比率を変えることでゴールドやブルー、グレーやピンクなど、さまざまなカラーに着色することも可能となっている。 石歯車やテンプの軸受けなど、稼動する部分の摩擦を防止するために使われる受け石や穴石のことを言う。現在では主に人造ルビーが使われているが、人造サファイアなどもある。その使用数によって17石や21石などと表記される。最低15石あれば単純な2針時計を組むことができる。歯車の多い複雑時計や耐久性の高い時計ほどその数は多いが、かつては天然のルビーを使用していたため、装飾目的として多用されたこともあった。 インカブロック1939年にスイスで発明されたアンチショック(耐震機構)のこと。ショックを与えたときにテンプの天真が折れないようにするため、バネが付いた穴石を使って支えている。呼び名が違うが同じ機能を持つダイヤショックやパラショックなどもある。 インダイヤルクロノグラフなどについているダイヤル(文字盤)の中にある小さなダイヤルのこと。30分または12時間の積算計や秒針などが主である。クロノグラフでは秒針がインダイヤルのものもある。 インデックス文字盤上にあるときを表すマークのこと。丸や棒のシンプルなタイプやアラビア数字を使ったアラビックインデックスなど、時計に個性を出すための大切なパーツ。 インナーベゼル(リング)数値などが描かれたリング状の部品で、ベゼルの内側=ダイアル外周部などに装備されたもの。通常はケースサイドに設置されたボタンやリューズで回転操作ができるようになっている。 ウイーク表示1年でダイアル内を1周する専用針や、1年で1回転する専用内蔵ディスク(回転盤)などを用いて、現在が1年のうち第何週目かを表示する機構。 機械式クロノグラフムーブとしては、後述のバルジューと並ぶ人気と実績を誇り、クロノ界の「2大ブランド」とも称されたスイスの著名ムーブメーカー。数多くのブランドにムーブを提供していたが、特にブライトリング社とは密接な関係を保ち、2つ目タイプ用のCal.175やその発展系である3つ目用Cal.178が、それぞれ「クロノマット」、「ナビタイマー」に採用されていたことでも著名。後にバルジューと合併した。 ウォータープルーフケース内への水分や湿気の浸入を防ぐための機能。Oリングやスクリューバック、ねじ込み式リュウズにねじ込み式防水機能を搭載した史上初の防水腕時計はイギリスのオイスター社が開発した。ロレックスは1926年からオイスター社のケースを採用したのである。現在では日常生活での汗や雨などに濡れても平気な30m防水からマリンスポーツやダイビングで使用可能な200メートル防水、ヘリウムガス排出バルブ付きで大深度の潜水にも耐えられる300m防水など、細かく分かれている。 受け歯車やテンプの真軸を支え、部品を保持するためのプレート。ブリッヂとも呼ばれる。 受け石歯車やテンプの真軸の軸先に取り付けられた石のこと。穴石とセットで使われて、摩擦を減らし、油を保持する目的に使われる。現在では主に人工ルビーが使われている。 腕時計手首に装着できる腕時計は19世紀頃に貴族女性の装飾具として作られた。1899年に起きたボーア戦争時に、イギリス兵が懐中時計を皮ひもで腕に着けたことで戦後商品化されるようになった。リストウォッチとも言う。 ウニコ2010年にウブロが発表した、初の自社開発クロノグラフ・ムーブメント。スペイン語の「ユニーク(唯一の、独自の)」が命名の由来。通常は裏ブタ側に設置されるコラムホイールを始めとするクロノグラフ機構を、ダイアル側に集約。スケルトン仕様のダイアルからその動きをいつでも堪能できるなど、その名のの通りユニークな構造を採用している。2010年バーゼル発表モデルの「キング・パワー ウニコ オールブラック」に搭載されている。 裏蓋ホコリや、水分などからムーブメントを守るために、ケースの裏側に取りつけられる蓋のこと。通常はケースと同じ素材が使用され、ねじ込み式やスナップ式で取り付けられる。防水時計にはテフロンやゴム製のパッキンが挟まれている。 裏輪列機械式ムーブメントにおいて、地板を挟んでも地盤側に設けられた輪列のこと。分車と時針を繋げる減速輪列やカレンダー輪列などがある。対して裏蓋側に設けられた輪列のことを表輪列と言う。 閏年1582年にローマ教皇グレゴリウス13世によって定められた、グレゴリウス暦の誤差を調整するための年。グレゴリウス暦では1年が365日と0.2425日となる。0.2425は400分の97なので400年間に97日の閏年を設ければ、調整ができるということになり、4で割り切れる西暦年を閏年としている。また、4で割り切れ、100でも割り切れる場合は閏年としないが、4と100で割り切れる年が、400でも割り切れる場合は閏年となる。 閏秒協定世界時(標準時)と地球の自転によって生じる時間の誤差を±0.9秒以内に保つための調整時のこと。 ウルトラスリム極めて薄いムーブメントと、そのムーブメントが搭載されたモデルの俗称。多くの部品で構成される機械式時計においては、極めて高い技術が要求される。 エアリーの定理振動している物体は外部からの衝撃によって等時性が変化するが、振動の中心軸で衝撃を受けた場合は振り幅が変化するだけで、等時性には影響がないという法則。テンプの等時性はこの定理に基づいている。 永久カレンダーパーぺチュアルカレンダーの項参照 エクステンションベルト広げることができる金属性ブレスレットのこと。繋ぎ目に板バネを入れることによって伸縮し、腕にフィットするようになっている。 エコ・ドライブシチズンが開発した、太陽光はもちろん蛍光灯の光でも発電する電池交換不要なクオーツ機構。光透過性に優れた文字盤を通過した光エネルギーが、文字盤下のアモルファスシリコンを主素材とする太陽電池(ソーラーセル)によって電気に変換され、その下層部分に設置された電池に蓄えられる構造になっている。 SSステンレススチールの略で、主にケースなどの素材として使われる。鉄と耐食素材のクロムを12%以上含んだもののことを言い、その含有成分などにより様々な種類がある。加工性や耐食性に優れた金属である。 SMHスイス最大の時計共同会社で日本のクオーツに対抗するため作られた巨大企業。母体となったのはETA社が中心となり、組織化されたエボーシュ連合でオメガ、ロンジン、ラドー、ブランパン、スウォッチ、ブレゲ、ジャケ・ドローなどがグループ傘下に収められている。1998年にスウォッチグループと改称された。 エスケープバルブ酸素とヘリウムの混合ガスを吸って、ダイバーの体を水圧に耐えられる状態にしてから潜水する飽和潜水を行うとき、時間内に浸入したヘリウムガスを排出させるためのバルブのこと。時計内のヘリウムガスを排出しないと、ダイバーが浮上するに従ってガスが膨張し、時計が破損してしまう。 エスケープメントテンプと輪列の間にあるアンクル、ガンギ車などで構成される、時計のリズムを性格にtが持つための機構部=脱進機構の総称。脱進機の項参照。 エスケープメント・ホイール日本ではガンギ車と呼ばれる。アンクルと共に脱進機構を構成する重要部品。 ETA(エタ)社1856年に創業したムーブメント供給会社。スイスのムーブメント業界では約8割のシェアを持ち、1925年にはエポーシュ連合を創立した。1982年に設立されたスウォッチはETA社のオリジナルブランドで、翌年の1983年にはスウォッチグループの前進となるSMHグループを結成した。 エタブリサージュ時計メーカーからそれぞれ作業を割り振って発注される、専門職人や工房の総称(外部委託製造業者のこと)。 ADAムーブメントの四隅にショックアブゾーバーの役割を果たすチューブを設置。チューブが衝撃や揺れを吸収することで、20mからの落下時に相当するショックや10ヘルツの振動にも耐える構造を持った、タグ・ホイヤーが開発した画期的機構のこと。 N夜光1993年4月に根本特殊科学が開発した高輝度長残光性蛍光体で、今までの夜行性塗料とは異なり、放射性物質を一切含まない安全な夜光塗料である。太陽光や蛍光灯などの光エネルギーを吸収し蓄え、暗い場所で蓄えた光エネルギーを放出することによって発光する。高い安定性を持ち環境に強く、照射する光が強いほど、明るく光るなどの特徴がある。 エボーシュムーブメントメーカーが製造した未完成のムーブメントのこと。多くの時計メーカーはこのエポーシュを仕入れて時計を組み立てている。スイスではETA社が約8割のシェアを誇っている。そのほかはフレデリックピゲ、レマニア、デプラ・デパズなどがある。 エリンバーヒゲゼンマイの素材に使用される特殊合金のこと。ニッケルが38%、クロムが12%、そして少量の鉄、マンガン、炭素、タングステンから構成されている。 LEDウォッチ発光ダイオードを用いて、時刻を表示する時計。ボタンを押すと数秒間、ダイアル上に時刻が赤や青などのLED数値で常時される構造になっている。 エルガF1マシンや航空産業にも使用されるハイテク合金の一種。軽量でありながら耐久性にも優れた素材で、焼入れなどの加工により赤やブルーなど鮮やかに発色する特性を持つ(主成分はマグネシウムで、その他チタニウムやジルコニウム、シルバーなどを含有する)。2010年の時計フェアではフランク・ミュラーやクストスがケース素材に採用して、注目度が高まっている新素材。 L.V.M.Hルイ・ヴィトンと、モエ ヘネシーが1987年に合併して設立された、フランス・パリに本拠を構える巨大企業グループ(傘下ブランドは50以上)。アパレル分野ではクリスチャン・ディオール、ジバンシー、ダナ・キャラン、セリーヌなど。飽食&時計分野では、ゼニスやタグ・ホイヤー、ショーメなどがこのグループに属している。 エル・プリメロ1969年にゼニス社とモバード社が共同で開発した自動巻きのクロノグラフムーブメントのこと。毎時3万6000振動の高精度ムーブメントだが、ロレックスでは毎時2万8800振動に改めて使用されていた。 エングレーブ裏蓋やムーブに彫金で模様を描くなどして装飾を施す伝統的な技法のこと。エングレーブができる職人をエングレーバーと呼ぶ。 エンジンターンドベゼル外観が航空機のプロペラエンジンヘッドに似た形状を持つ、ベゼルの装飾技法。 エンドピース穴ケースとベルトを繋げるために、バネ棒を固定しておくための小穴のこと。ラグ部分に開けられており、ラグを貫通しているものと内側に溝が彫ってあるタイプがある。 エンボスインデックス文字盤を裏側からプレスして、数字が浮き上がるように加工したインデックス。 エンボス文字盤盤をプレス加工して凹凸を付けた文字盤のこと。大量生産に向いている。 オイスターケースイギリスのオイスター社が開発した世界初の完全防水ケース。1926年にロレックスが採用し話題となった。金属の塊をくり貫いて作られたケースに、リュウズと裏蓋をねじ込み式にすることによってケース内への水分や垢の進入を防ぐことに成功した。基本構造は当時のものと未だに変わっていない。 オイスターロックブレス腕に大きな衝撃を受けた際に、その衝撃などでクラスプのロックがはずれないよう、上から細い板状部品を覆い被せることで(2重に)ロックする方式を採用したロレックスブレスレットのこと。 オイル機械構造を持つものなら、摩擦や磨耗を低減するために必ず必要なのがオイルである。巻き上げ機構部分にはグリス系、金属部分にはモリブリデン系、穴石や脱進機などには低粘度のオイルというように、使用する部分によって異なった成分のオイルが使い分けられているが、最近ではどのパーツにも共通して使うことができる万能オイルも使われている。油とも言う。 オクタゴンケース英語で「八角形(オクタゴン)」を意味する言葉通り、8つの角で構成される時計ケース。 オシドリ時刻合わせに必要なパーツのひとつで、巻真と噛み合っており、リュウズが引かれるとオシドリも引っぱられ、同時にカンヌキを押す仕組みになっている。それによってツヅミ車はキチ車から離れ、小鉄車に連動し時刻を合わせることができる。 オートクロノグラフタイマーとストップウォッチの2つの機能を持ち、タイマーが終了すると同時に、時間経過の測定を自動的に行ってくれる機能のことを言う。 オートマタ自動からくり人形という意味で、18cのジャッケ・ドローがツンギンブバードの製作者として有名。文字盤などにからくりや仕掛けの機構をもった時計のこともこう呼ぶ。 オートマチック腕を動かすことによって重力で回転するローターが自動的にゼンマイを巻き上げるシステム。すなわち自動巻きのこと。毎日使用していればゼンマイを巻かなくても動き続ける。 オニオン型リューズ横から見た形状が玉葱に似た、クラシカルな大型リューズ。 オーバーホール時計の中身を分解し、修理や洗浄、注油などをすること。機械式時計の場合、油が切れることによりパーツが磨耗したり、カスなどが溜まって動きに支障をきたし時間がくるってきてしまう。時計を長持ちさせるためには、2年から5年に1回のサイクルでオーバーホールをすることが望ましい。 オープナーケースの裏蓋を開けるための道具。時計によって防水機能に優れたねじ込み式蓋用のものや、はめ込み式のもの、ロレックス専用に作られたものなど様々な種類のオープナーがある。 表輪列地板をはさんで裏蓋側に設けられた香箱車、2番車、3番車、4番車で構成される輪列のこと。ゼンマイの動力を増速させて脱進調速機へと伝える働きをする。対義語は裏輪列。 Oリング車やバイクなどのパーツにも使われる円形のゴムパッキン。時計ではダイバーズウォッチなど、完全防水を求められる時計に使われることが多い。特殊な合成ゴムを使うことによって弾力性に優れ、パーツ間の隙間を塞ぎ優れた気密性をもたらす。 温度差時計気温が変化することによってドラム内のガスが膨張、収縮を繰り返し、ゼンマイが巻かれるという仕組みを持った時計。現在ではジャガー・ルクルトが商品化しているが、考案されたのは約70年前のこと。 |
用語集【か~こ】 |
外装ケースや文字盤、針などムーブメント以外の部分の総称。ムーブメントを保護するケース、時間を示す文字盤と針、ベゼルなど時計を構成する上では必要不可欠なパーツばかりである。 懐中時計主に16世紀から20世紀初頭まで使われていた文字通り懐に入れて使う時計。蝶番開閉式の蓋を持ち、チェーンやひもを付けて衣服に付けたりポケットに入れたりして携帯した。蓋には美しい装飾が施され、美術品としての価値も高いものもあった。しかし、20世紀になると腕時計が主流となり人気は衰退していった。提時計、ポケットウォッチなどとも言う。 回転錘ローターの項参照 回転ベゼル経過時間や第2時刻を表示するなど、様々な使い方ができる回転式のベゼル。1929年に海軍将校のP.V.H.ウィームスが考案し、ロンジン製の航空時計に搭載されたのが史上初である。逆回転しないラッチェット式の回転ベゼルは、ロレックスのターノグラフが最初となる 角穴車ゼンマイを巻くときに必要な歯車で、中央の歯車の穴が角形になっている。そのため、歯車と軸がしっかり噛み合わさりゼンマイを巻き上げる強い力にも耐えられるようになっている 角穴ネジ香箱真と同軸上にある角穴車を香箱真に留めるためのネジ。ドーム型のものや、ねじ込むと角穴車の面と同じ形になるものなど形状は様々。 ガスケットリュウズ部分の防水性を高めるために使用される合成のゴムパッキンのこと。リュウズ部分は一番水分が入りやすいので、2重または3重に取り付けられる。ダイバーズウォッチなどの防水が必要な時計には必ず取り付けられている。 カップリングクランチクロノグラフに付いているストップウォッチ機能の鍵となるパーツで、スタートを押すとトランスミッションホイールとクロノグラフランナーを連結する働きをする。ストップを押すと解除される。 カップリングクラッチホイールクロノグラフ機構において、4番車と連動して常に回転しているドライビングホイールの動力をクロノグラフランナーに伝える役目をする。スターとボタンを押すとピラーホイールの歯の間にカップリングクラッチの先端が落ちる。それと同時にトランスミッションホイールがドライビングホイール、クロノグラフランナーと噛み合うようになり、1分間を計測するクロノグラフ秒針が動き出す。 カナ車を構成するパーツのひとつで、歯車の動力を伝える部分。歯車の上または下に付いた歯切りした部分で、このカナに歯車が噛み合わさり他の歯車が回るようになっている。それぞれ2番歯車についているカナを2番カナ、3番歯車についているカナを3番カナと言う。 カーベックス手首にフィットするように手首の形に合わせてカーブさせているケースのこと。1937年にスイスのグリュウエン社が発売したものは、ケースに合わせてムーブメントの形状もカーブしている。 カボション面がカットされた宝石に対し、つるつるにカットされたものを指す。時計ではリュウズの先端に取り付けられた宝石のこと。装飾目的として付けられている。 カム式クロノグラフパーツを減らすため、ピラーホイールの代わりにカムを使用した廉価版クロノグラフのこと。基本的な役割はピラーホイールと変わらないが、ピラーホイールは回転運動なのに対し、カム式は軸を中心とした首振り運動となる。 ガラス文字盤を保護する風防ガラスのことを言う。昔は無機ガラスが使われていたが現在ではアクリル樹脂や人口サファイアが使われている。アクリル樹脂は安くて割れにくく軽いという利点があるが、キズが付きやすく状況によっては変色することもある。逆に人工サファイアは傷つきにくく変色もほとんど無いが値段が高い。レイズド・クリスタル、フラット・クリスタル、クリスタル・コンケイブ、ラウンド・ドーム・無反射コーティングなど様々な形状のガラスがある。 カルーセルウォッチ時計の向きによってかかる重力による姿勢差を自動補正するというトゥールビヨンウォッチと異なる点はケージが4番車ではなく、3番車の周りを回転するという点にある。 カレンダー機構デイト表示やムーンフェイズ、パーペチュアルカレンダー、月、日、曜日を表せるトリプルカレンダーなど、シンプルなものから複雑機構まで月や日にちなどを表示する機構のことを言う。 側ケースのこと。ムーブメントが組まれた時計本体のことを言う。金、銀、ステンレス、真鍮など素材は様々 側開けケースの裏蓋を開ける道具。オープナーの項参照 側留めネジムーブメントと側(ケース)を留めるためのネジ ガンギカナ4番車から伝わってきた動力をカンギ車へと伝える役割をする小さな歯車。つまりカンギ車の軸の周りに付属しているカナのこと。 ガンギ車アンクル脱進機に使われるパーツのひとつ。アンクルの2つのツメ石が交互に噛み合うように作られた歯車で、テンプに一定の力を与え左右に回転運動をさせる役割と、テンプからの振動周期を規則正しく歯車に伝える役割を持っている。 緩急針時計の進み具合を調整する針で、ヒゲゼンマイに接していて針を左右に動かすことによってヒゲゼンマイの有効長を調整している。 カンヌキ時刻合わせに必要なパーツでツヅミ車の溝に設置されている。リュウズに引っぱられたオシドリによってカンヌキが押され、ツヅミ車と小鉄車を噛み合わせる。そして小鉄車から中間車へと伝わり日の裏車を介して筒カナを回し、時刻を合わせることになる。 機械式時計巻き上げたゼンマイが戻る力を動力にして針を動かす時計のこと。リュウズを巻くことによってゼンマイが巻かれる手巻きと、ローターが回転することによってゼンマイが巻かれる自動巻き(オートマチック)とがある。機械時計、メカ時計などとも言う キズ見時計修理の時などに、細かい部品を見るためのルーペ。メガネに付けるタイプや頭に固定するバンドタイプ、また倍率によって様々な種類がある。 キチ車巻き上げ輪列パーツのひとつで、巻真を通してリュウズと連結されている。リュウズを巻くとキチ車が回り、接している丸穴車が回転してゼンマイが巻き上げられる仕組みになっている 逆回転防止ベゼル主にダイバーズウォッチに使われる一方向のみに回転するベゼルのこと。ダイバーが潜水時間を測るときに使うため、誤って逆回転してしまい、測定時間が狂わないようになっている。 ギャーシェ彫り文字盤に掘り込まれた細かい模様のこと。現在では機械による掘り込みや型押しのブレスが主になっているが、ブレゲなどの一部のブランドでは職人による手旋盤で彫り込まれている。装飾目的の他に光の反射を防止する効果もある。 ギャビノチェ18世紀のスイスで活躍した時計職人の総称。ヴァシュロン・コンスタンタンの創業者ジャン・マルク・ヴァシュロンなどの独立性が強い職人で、キャビネ(屋根裏部屋)を工房としていた職人が多かったため、こう呼ばれるようになった。 キャリバームーブメントの型式を表す用語。「Cal.」で表示されるムーブメントのサイズや機構を数字やアルファベットを使って表す場合が多い。例えばCal.3541やCal.30CHなど。 協定世界時(世界標準時)国際協定により定められた世界共通の標準時で、世界各国の標準時はこの協定世界時を基準にして決められている。原子時(UTC)をもとに閏秒を挿入することによってグリニッジ標準時との差を調整している。現在のフライトスケジュールはこの協定世界時を基準にしている。 均時差視太陽時から平均太陽時を引いた差のこと。視太陽時とは実際に1日に太陽が動いている時間で、平均太陽時とは1年の太陽の動きの平均時間のことを言う。 空気潜水用防水最低100mの潜水に耐えられる防水性能のことで、JIS規格とISO規格によって検査方法と要求事項が規定されている。圧縮空気を吸って潜水するスキューバダイビングレベルの潜水深度に耐えられるよう規定されている。スキューバ潜水用防水とも言う。 クオーター・リピーターミニッツ・リピーターから、分単位の数を知らせる鐘の音色を省略したモデル(リピーターの項目参照)。 クオーツムーブメント電池を動力源として、水晶振動子と電子回路、ステップモーターで調速&運針を行なう時計のこと。調速の基準が機械式時計が毎秒5~10振動のテンプに依存するのに対し、クオーツ式は水晶振動子の毎秒3万2768振動が基準。そのため精度も機械式に比べ数倍~数十倍にアップし、機械式時計の一般的なモデルが1日の精度誤差が平均±10~20秒前後であるのに対し、クオーツ式の一般的なモデルでは1ヶ月の精度誤差が平均±15~20秒前後となっている。 鎖引き装置ゼンマイはほどけていくにつれてトルクが減少していく。その減少を補いムーブメントに均一に動力を伝える働きをする。 クッションケースその名の通りクッション形をしており、文字盤は丸型のタイプのケース。カジュアルで優しい印象を受けるため、女性に人気の形。 グラスヒュッテドイツの時計産業の中心地でザクセン州、ドレスデンの南方に位置する。その歴史は19世紀末から続いたが中断の後、近年復活を果たした。今でもグラスヒュッテオリジナルやランゲ&ゾーネ、ノモスなどの高級ブランドが集まっている。 グラブツースレバー脱進機イキリスの時計師トーマス・マッジが18世紀末頃に考案した、2つの爪を装備したアンクルとレバー、ガンギ車でテンプの動きを制御する脱進機。ガンギ車とテンプの回転を、レパーを介してアンクルが制御する構造になっている。作動安定性と高精度化に優れた特性を有し、現在の脱進機構のルーツとなったメカニズムで、現在も機械式腕時計のほとんどにこの方式の脱進機構が採用されている。 グランドコンプリケーションウォッチうるう年も無調整で自動表示できるパーペチュアルカレンダー、重力による姿勢差を自動補正するトゥールビヨン、ストップウォッチ機能のクロノグラフ、時刻を知らせるミニッツリピーターの4つの複雑機構をすべて搭載している時計のこと。1つでも高い技術を要する複雑機構を4つ組み合わせるので、膨大な時間と高度な技術が必要となる。オーデマピゲなど一部の高級ブランドに見られる。その名の通り最高技術の結晶であり、至高の一品である。 グランドストライク自動的に正時と15分おきに音で現在時刻を知らせ、リピーターと同じように操作することによっても、現在時刻を知らせることができる機構。毎時と15分おきに自動的に鳴るものをグランソヌリ、毎時に自動的に鳴るものをプチソヌリと言う。これに対し、任意の時間を知らせる機能をミニッツリピーターと言う。これに対し、任意の時間を知らせる機能をミニッツリピーターと言う。複雑機構のひとつ。 クル・ド・パリ「パリの爪」の意味を持つ宝飾デザインで、フランスで300年以上継承される伝統あるデザイン。小さなピラミッド型が連なったような形をしていて、腕時計にはベゼル部分に使われる。アブラアン=ルイ・ブレゲが初めて時計に採用した。 車ゼンマイに蓄えられた動力を香箱車からカンギ車まで伝えるためのパーツ。ホゾ、カナ、ウデ、リム、歯車から構成されていて2番車から4番車まである。2番車は1時間で1回転し、4番車は1分間で1回転する。 クロコダイル本来はアリゲーターやケイマンなどと同様にワニの一種を指すが、革皮用語ではワニ革の総称として使われる。ベルトの表革として使われる高価な素材。 クロック一定の姿勢で動いている置き時計や掛け時計、柱時計などの総称。ラテン語で鐘を意味する「cloccal」が由来となっている。 クロノグラフ標準の時計機能にストップウォッチ機能が付いた時計のこと。始動、停止、再始動、リセットができ、60秒で1周するクロノグラフ秒針が30分計や12時間計と連動して経過時間を測定する。なお、初めて商品かされたクロノグラフは懐中時計で、1897年に発表されたロンジンのルグランである。 クロノグラフランナークロノグラフ針に付いている1分間で1回転する歯車。スタートボタンを押すとドライビングホイールからトランスミッションを経由してクロノグラフランナーが回転、そして計測が開始される仕組みとなっている。 クロノプラン任意に指定する時刻を記録することができるクロノグラフのこと。クロノグラフやカレンダーなどの複雑機構を得意とするモバード社が独自に開発したもの。 クロノマチックブライトリング、ホイヤー、ハミルトン、ビューレンが開発した自動巻のクロノグラフムーブメント(キャリバー11)で、リューズが左側にくるのが特徴。トラブルが多いため、すぐに製造中止となった。 クロノメーター規格スイスの時計製造協会が1957年に制定した規格で、15昼夜かけて厳しい試験が行なわれ、その試験を通った時計にだけ与えられる称号。現在はC.O.S.C(クロノメーター検定協会)が行なっている。5種類の置き方と3つの異なる温度に24時間さらし続け、毎日制度を検査する。詳しくは1~2日目はリュウズを左にして(垂直姿勢)温度23℃。3~4日目はリュウズを上にして(垂直姿勢)同じく23℃で。5~6日目は23℃でリュウズを下にして(垂直姿勢)。7~8日目は23℃で風防側を下にして(水平姿勢)。9~10日目は23℃で風防側を上にして(水平姿勢)11日目は8℃で風防側を上にして(水平姿勢)。12日目は23℃で風防側を上にして(水平姿勢)。13日目は38℃で風防側を上にして(水平姿勢)。14~15日目は再び23℃でリュウズを左にして(垂直姿勢)、という試験が行なわれる。この結果日差が-4秒から+6秒以内の場合、公認クロノメーターとして認定される。 クロワゾネ極細のゴールドワイヤーで図柄を描き、そこにエナメルを施していく伝統的な技法。時計では文字盤に使われる。高度な技が要されるため、職人の数は少ない。和名は有線七宝と言う。 軍用時計時計メーカーがアメリカ国防省の定めたミル・スペックと呼ばれる規定に基づき製造、供給する時計のこと。 携帯精度気温5℃~35℃環境下で、腕時計を最低1日8時間以上装着しているときの精度のことを言う。腕時計は気温5℃~35℃の間で最も精度が安定するように調整される。 ケース文字盤やベルト部分を除いた胴体部分のことを言う。素材や形は様々で、真鍮、金、プラチナ、銀、SS、プラスチックなどの素材とオクタゴン、オーバル、クッション、ラウンド、トノー、レクタンギュラーなどの形が一般的である。 月差1ヶ月間における時刻の遅れや進みを表す言葉で、月差3分などと表す。機械式時計においての平均月差は10分である。 原子時計原子や分子の発生する一定周波のエネルギーを利用することによって、30万年から160万年に1秒の誤差しか生じない超高精度な時計。世界標準時はこの原子時計を基準に定められている。 コーアクシャル脱進機時計技術者であるジョージ・ダニエルズが開発した脱進機構で、通常2つのツメを持ったアンクルを使用するが、コーアクシャル脱進機は3つのツメのアンクルを使用する。アンクルの3つのツメと降り座に付いたツメ、そしてガンギカナがあることによって作業が分担されることになり、磨耗が軽減されてメンテナンス時期も長くなる。磨耗が少なく、潤滑油がほとんどいらないため安定した制度を保つことができる。 コインエッジベゼルコインエッジベゼルや44㎜径のビックフェイスが、クラシカルで精悍な印象を際立たせるオリス「ビッグクラウン スモールセコンド ポインターデイ」ベゼル部の光の乱反射を防ぎ視認性を向上させるため、コインの緑部分のようなギザギザの紋様が刻まれたベゼルのこと。 高振動テンプが1G時間に振れる回数を振動数と言い、この数が高いほど高精度とされている。一般的な振動数は1万8000~2万8800で、高振動(ハイビ-ト)とは2万1600振動より上のもののことを言う。 香箱機械式時計において、動力源となるのがゼンマイ。そのゼンマイを収納している箱型の歯車のことを香箱と言う。香箱の中のゼンマイが巻かれ、そのゼンマイが戻る力によって香箱が周り、香箱の歯車に接している2番カナへと動力を伝えている。 香箱真香箱にあり、動力源の一番はじめとなる軸。リュウズからキチ車、丸穴車へと伝わってきた動力を角穴車と組み合わさり、ゼンマイを巻く仕組みになっている。ゼンマイを巻き付ける真のこと。 香箱蓋ゼンマイが飛び出さないように抑えておく蓋のこと。ゼンマイと香箱真は香箱本体と香箱蓋に挟まれた形となっている。 COSCスイスのニューシャテルに本部を構える、公式クロノメーター協会(コントロール・オフィシャル・スイス・デ・クロノメーター)の略称。公的な検査機関が実施したクロノメーターテストで、一定以上の成績をあげた時計に対して、高精度時計の公式評価証明書である「クロノメーター」を発行する機関。 コートドジュネーブさざ波をモチーフにした装飾模様の一種で、時計では受けやローターなどに施されることが多い。その美しい模様は高級時計の証とされ、古い歴史を持つ。 コハゼ香箱が逆回転しないように取り付けられる装置でコハゼバネで規制されている。様々な種類があるが、一般的に時計には退却型コハゼが使用される。 コラムホイールクロノグラフの作動を制御する部品で、ピラーホイールともいう。上段は6~9程度の歯車の付いた円柱状で、下段はキアの付いた歯車の2段構造になった部品。円柱状の歯車にクロノグラフのアームやカム類が乗り上げたり、はずれたりすることで、クロノグラフのスタート&ストップを制御する構造になっている。一般的な「カム式」に比べ操作感が滑らかで、タイムラグなども少ない確かな作動性を有するが、組み込みや調整に熟練職人の手間を要するため、主に高級モデルに採用されている。 ゴールドモデル「金無垢」モデルのこと。一般にゴールドウォッチという場合、金メッキや金張り加工のものは、これに含まれないことが多い。 コンバーチブルケース風防を守るために裏返すことができるケースのこと。代表的なのはジャガールクルトのレベルソ。元々はポロ競技用として作られた。 コンビネーションケース異なる2つの素材、また2色を合わせて作ったケースのこと。ベゼルに金、ケースにステンレススチールの組み合わせが一般的。 コンプリケーションウォッチパーペチュアルカレンダー、トゥールビヨン、ミニッツリピーター、スプリットセコンドなど複雑機構がいずれか、または複数搭載されている時計のこと。製作には時間と高い技術を要するため、たいへん高価である。 |
用語集【さ~そ】 |
サイクロップレンズ離れた位置からでも日付を読み取りやすくするため、ガラスを加工して日付け数値を拡大表示するためのレンズ。通常は平坦なサファイクリスタルの表面に、レンズガラスを接着加工してある。 サーティファイド・マスター・ウォッチメーカー(CMW)アメリカで始まった時計職人のための技術試験。一次、二次と5日間にわたり厳しい試験が行なわれ、合格者にはヨーロッパの時計マイスターと同等の技術資格と認定される。日本では1954年から日本の時計産業を復興し、時計職人の技術力を上げることを目的に導入している。学科試験のほかに巻真を作ったり、腕時計を修理したり調整技術の試験など、難解な実技試験が用意されているが短期間で廃止になった。 サテン仕上げケースやブレスなどの金属表面に、サテン繊維のような細かいスジ模様が入った加工方法。光の反射を抑え、シックでスポーティーな印象に時計を装うことができる。ちなみに、このタイプの加工が施された時計は、研磨剤成分を含んだクロス類で磨くと、サテン部分にムラができたり、ハゲてしまうこともあるのでケアの際には注意が必要。 サファイアガラス人工的に作られたサファイアのガラスだが、天然サファイアと同等の硬度を持つ。人工サファイアをカットし研磨したもので、傷つきにくく防湿性に優れ、透明度が高いので文字盤が見やすいなどのメリットがある。加工が難しいため高価で、主に高級腕時計の風防に使われている。 サボネット式ケースケースの表や裏に開閉式のカバー=蓋を付けた時計のこと。 ザリウム低アレルギー物質で、高硬度なジルコニアを主成分とする合金。外科手術用のメスなど医療器具にも使用される素材で、金属アレルギーを発生しにくく、耐久性や耐腐食性にも優れた特性を持っている。 30分積算計クロノグラフ機構をスタートさせると、センターのクロノグラフ秒針と共に動き出す、「分」を積算表示するサブダイアル。クロノグラフ秒針が1周するごとに1分ずつ針が目盛りを刻み、30分までを計測することができる。 三針時計時針、分針、秒針のみのシンプルな時計のこと。三針が全てセンターにあるタイプや、スモールセコンドなど秒針が離れたタイプも三針時計と言う。日付窓の有無は関係ない。 3番カナ2番車から動力を受けて3番車を回転させるための歯車。3番車の真軸を覆うように付いている。 3番車2番車から伝わってきた動力を4番車へと伝える働きをする増速歯車。基本輪列を構成するパーツのひとつ 地板ムーブメントのパーツを組み込むための母体となる金属製の基盤のこと。ゼンマイや脱進機など様々なパーツがこの地板と受け板の間に収められて動いている。 GMTグリニッジ・ミーン・タイムの略で、1884年に国際子牛線会議で決められたグリニッジ標準時のこと。イギリスのグリニッジ天文台での天体観測を元に決められた時刻で、昔は世界標準時とされていたが現在では原子時を元にした協定世界時が使われている。また、第2時刻が読み取れるワールドタイム機能を意味することもある。 時差地球上の2地点間での標準時間差のこと。経度15°で1時間の時差となる。グリニッジ標準時が基準となっているため、イギリスから何度差があるかで決まる。日本とイギリスとの経度の差は135°なので時差は+9時間となる。 時差修正時計を動かしたままで、時間単位の時刻修正ができる機能のこと。 指示差時計が示す時間と標準時間(協定世界時)との差 シースルーバック裏蓋に透明な素材(サファイアガラスなど)を使うことによってムーブメントの動きを見ることができる仕様のこと。ブリッジの不要な部分を切り抜いて、両面から透けて見えるものをスケルトンと言う。どちらも高級時計に見られる。 姿勢差地球には重力があり、重力は一定方向で一定の大きさでも脱進調速機は様々な姿勢になる。その重力の影響によって生じてくる誤差を姿勢差と言う。置き時計や掛け時計なら一定だが腕時計は常に時計が動いているため誤差が生じやすくなる。その誤差を減らすための機構がアブラアン・ルイ・ブレゲが発明したトゥールビヨン機構である。 自動巻きムーブメントローターと呼ばれる半円形の部品が腕の動きによって回転し、その回転が歯車に伝達されることで、自動的にゼンマイを巻き上げる機構を搭載したムーブメント。 ジャイロマックステンプテン輪の外周上に付いているチラネジの代わりに、天輪上に取り付けられたC形のピンに調整ウェイトをはめ込んだテンプ。1949年にパテックフィリップ社が特許を取得した調速機構で、チラネジ付テンプよりも計時制度が向上した。 シャンパンゴールドグラスに注がれたシャンパンのような、透明感のある輝きを放つゴールドのこと。 ジャンピングアワー分針が1周する動力を利用して時を示す文字盤を瞬時に動かす機構。つまり、正時になると同時に文字盤の数字も動く機構のこと。 18金イエローゴールド一般的には純金75%、銀と銅を25%の合金を指し、18金イエローゴールドと呼ばれる。ケースやブレスレットの素材として使われているが、ムーブメント部分にまで及ぶメーカーもある。 ジュネーブサロン1991年にカルティエグループがジュネーブで開催した内覧会で、翌年から年1回のサイクルで時計展示会として開催されることになった。現在ではリシュモングループを中心として14ブランドが参加している。 ジュネーブ・シールジュネーブ市が制定した、クロノメーター規格よりもさらに厳しい規格に合格した時計に与えられる認証。ムーブメントの品質や組み立てなど、最高レベルの基準にクリアしたムーブメントにはジュネーブ市の紋章が刻印される。取得しているのはパテックフィリップが中心。 ジュネーブ・タイム・エキシビション(GTE)2010年からスイス・ジュネーブで開催され始めた、新たな新作時計発表会。アントワーヌ・プレジウソやアラン・シルベスタイン、hD3コンプリケーションなど、38ブランドが参加して行なわれた。 植字文字盤に小穴を開け、はめ込むタイプのロゴやインデックスのこと。またはインデックスなどを取り付けることを指す。アップライトとも言う。 シリアルナンバーひとつひとつの時計に付けられる通しの固有番号。シリアルナンバーで製造年月を管理しているメーカーもある。 シリコン製ガンギ車通常は真鍮や合金で製造されるガンギ車を、特殊なシリコン素材としたもの。金属製のガンギ車と異なり、アンクルのツメと接触しても摩擦や磨耗が極端に少ないので注油の必要もなく、長期間の安定した精度維持と抜群の耐久性を得ることができる。 シリンダー脱進機ガンギ車の歯がテンプの円筒形回転軸と噛み合って作動する脱進機で、古典的な柱時計などに使われていた。精度は高いものではない。 振動子振動する物体のことを言い、時を刻む基準となる。調速機に使用される振り子やテンプなどがある。 振動数振り子時計では振り子が機械式時計ではテンプ、クォーツでは水晶が揺れる回数のことを言う。基本的に振動数が多くなれば時計の精度が上がるが、その分摩擦や磨耗も激しくなる。そのため耐久性に問題が出てくるので、高振動数だからといって必ずしも高精度ということにはならない。 スイス公認クロノメーター協会ジュネーブに本部を置き、時計の品質向上を目的とし設立されたクロノメーター規格の試験を行なっている機関。その他時計精度の検査なども行なっている。 スイープセコンドクオーツ時計はステップモーターで運針を行なうため、通常はカチッカチッと1秒ずつを区切った独特な運針を行なうが、特殊な輪列機構を用いることで、機械式時計に似た滑らかで流れるような運針を行なう、クオーツ時計の秒針。 スウォッチグループSSIHグループのリーダーであったオメガ、ASUAGリーダーのロンジンなどが結集して組織された時計企業連合。スイスでは最大勢力を誇るグループで、オメガやブレゲ、ブランパン、ティソ、ロンジン、ラドー、グラスヒュッテ・オリジナルなど著名時計ブランドを始め、ムーブメント製造メーカーとして著名なETAなどもここに属している。 スクエアケース四角形のケースのことで、基本的には文字盤も四角形のデザインをしている。 スクラッチプルーフ1962年にラドーが開発した超硬合金素材。炭化チタンニウムとタングステンから成り、特殊加工技術で磨き上げられているので耐傷性に優れている。 スクリューバックダイバーズウォッチなどに多くしようされるねじ込み式の裏蓋のこと。気密性と防水性を高めるために、通常パッキンと組み合わせて使われる。各メーカーのモデルに合わせて、専用オープナーがあることが多い。 スケルトン地板やブリッジを透かすことによって、内部構造が両面から見えるようになったもの。シースルーはシースルーバックと言い、裏蓋が透明で機械が見えるもののこと。 スケルトン針時計、分針の全体または先端が菱形にくり貫かれたものは通称「亀頭針」と呼ばれる。 ステンレススチール鉄にクロム(Cr)やニッケル(Ni)を混ぜた合金。クロム成分が空気中の酸素と化合して表面に保護皮膜を作るため、サビが発生しにくい特性を持つ。一口にステンレススチールといっても、マルテンサイト系やフェラサイト系、オーステナイト系など、含有成分や用途によってその種類は数百種に及ぶが、時計のケースやブレスレットには加工が比較的容易で防錆性に優れた、オーステナイト系の304、316Lが主に使用されている。 スプリットセコンドクロノグラフラップタイム(中間地点から次の地点までの経過時間)を計測することができる機能を持ったクロノグラフ。スタートを押すと2本のクロノグラフ針が計測を開始する。途中でストップ用のプッシュボタンを押すと1本だけ止まり、経過時間を計ることができる。再びプッシュボタンを押すと1本だけ止まり、経過時間を計ることができる。再びプッシュボタンを押すともう一本の秒針に追いつき、再度測定し始める。 スプリングドライブ1998年にセイコーが開発したオリジナル機構。ゼンマイを動力源としながらも、調速をクオーツのようにIC回路と水晶振動子で行なう方式の時計。ICやモーターの駆動電力はゼンマイで発電されるため電池は不要。環境に優しい新世代の駆動方式として、世界中の時計関係者に高く評価されている。 スムーズテンプバランスを調整するチラネジやアジャストスクルーネジがないシンプルなテンプ。設計段階でバランス調整が行なわれている。温度による膨張率の少ない金属で作られていて、チラネジ付きのテンプのように温度補正の必要がない。 スモールセコンド一般的な時計は秒針が時針、分針と同じセンターに付いている(センターセコンド)が、スモールセコンドとは時分針から離れた場所に秒針を持つインダイヤルのことを言う。小秒針とも言う。 スモールダイヤルインダイヤルと同義語 スライディングギアクロノグラフでストップウォッチをリセットする時に働くギアで、反時計回りに移動することによってスライディングギアに付いた歯車とクロノグラフランナーに付いた送り爪との接触を避ける。 スワンネック形状が「白鳥の首」に似ていることから名付けられた、誤差を微調整する緩急針の一種。組み立てや調整には繊細で緻密な熟練技術を要するため、主に高級時計に採用されている。 世界時計文字盤やベゼル部分に世界の主要都市名と標準時が書かれており、それを合わせることによってその都市の時間を表示することができる時計のこと。海外旅行などに行っても時差を計算することなく時刻を読み取れる。ワールドタイムウォッチとも言う。 セキュリティプッシャーオメガ「シーマスタープロプロフ1200M」のケース上部に設置されたボタン。誤作動を防ぐため、このボタンを押している間だけ回転ベゼルを操作することができ、ボタンを離すとロックして固定される構造になっている。 セキュリティプッシュボタンプッシュボタンから湿気や水分が浸入しないよう、ネジ込み式のロック構造にしたクロノグラフ操作用オタンのこと。 セコンド針セコンドつまり秒針のことを指す。文字盤中央にあるものをセンターセコンドと言い、インダイヤル内にあるものをスモールセコンドと言う。 セミ・パーペチュアル4年に一度、閏年の2月の末日だけ調整すれば、そのほかの年&月は自動的にカレンダーを正しく表示する機構。 セラミックス狭義では陶土などを原料として焼結加工した陶磁器やガラス、セメント製品。広義では、炭化物や窒化物その他の各種原料を素材とし焼結した加工物全般を指す。耐摩耗性や耐熱性、耐腐食性に優れた特性を持ち、時計の場合もケースやブレス、ベゼルに広く活用されている。 セリタ1950年創業のムーブ製造メーカー。もともとはETAなどからエボシュや部品を仕入れ、アッセンブリーするムーブ製造ブランドとして創業。 瀬戸引き(ダイヤル)薄い金属の上に瀬戸を貼り付けてある陶器のダイヤルのこと。ポーセリンダイヤルとも言う。1930年頃まで高級時計などに使われていたが、厚くて加工が難しいので新素材が開発されるにしたがってその役を終えていった。 センターセコンド秒針が、長・短針と同じセンター軸に設置された時計のこと。日本では中3針ともいう。 センター内臓ウォッチ湿度や気圧、方位などを感知するセンサーをケースに内臓することで、現在地の高度や気圧、湿度、方向(コンパス)などをダイアル上にリアルタイム表示できるクオーツ時計のこと。 センターミニッツレコーディング文字通りセンターの針が分積計算針になっていて、インダイヤルの分針を持たないクロノグラフのこと。スタートボタンを押すと、センターの分針が長針と同じように連続して動きながら測定を開始する。 ゼンマイ機械式時計の動力源。香箱に収められていて、香箱真に巻かれたゼンマイが、戻る力を利用して機械式時計は動いている。昔はスチールを使用していたが、現在ではニバフレックスなどの特殊鋼が使われている。 ソーウインドグループジラール・ペルゴ、ジャンリシャールを擁する企業グループ。2010年6月には提携したボッテガ・ヴェネタがブランド初の腕時計も発表している。 ソネリ毎正時や15分ごとに、自動的に鐘の鳴る装置。鐘はボタン操作で任意に作動させたり、音が出ないようオフ状態に設定しておくこともできる例が多い。ちなみに毎正時と15分ごとに鐘の鳴るものはグランソネリ、毎正時と30分ごとに鳴るものはプチソネリと呼ばれている。 |
用語集【た~と】 |
ダイアルいわゆる文字盤のことで、時刻を表示する目盛や数字、マークが記されている部分のこと。その素材やデザインは様々で時計の顔を決定する重要なパーツ。 耐磁性時計が外からの強い磁気に耐えられる性能。時計は磁気を受けることにより帯磁し、誤差を生じてしまうことがある。 衝撃性衝撃に耐える性能のことで、JIS規格では水平な硬い木の面に1mの高さから落とした場合に耐えられる時計を耐衝撃ウォッチと規定している。 耐振軸受テンプを衝撃から守り安定した動作ができるように、軸を衝撃から保護する機能を持った軸受けのこと。インカブロック(耐震装置)を構成するパーツのひとつ。耐衝撃軸受けとも言う。 タイドクロノグラフ潮の満ち引きを計測することができる潮位計目盛りが付いたクロノグラフのこと。漁業関係者や港湾関係者のために開発された。 ダイバーズウォッチ防水性に優れた潜水に使用できるスポーツウォッチのこと。最低でも100m以上の潜水が可能であることがISO規格で決められている。 ダイレクトフライト機能ダイアル4時位置のディスク表示から、都市名(世界26都市&UTC)を選択すれば、その都市の現在時刻や日付けなどが瞬時に表示される、シチズンが開発したオリジナル機構。 タキメータークロノグラフに付いている平均速度を測定することができる機能のこと。発進したときにスタートボタンを押してクロノグラフを始動させ、1km通過時点でストップする。その時にクロノグラフ針が指しているタキメーターの目盛りの数が平均時速となる。 多軸時計アラームやタイムカウンターなど時計以外の機能を持つ時計のこと。30分計や12時間計を搭載したクロノグラフなどのこと。 脱進機ガンギ車とアンクルから構成され、輪列と調速機の間に位置している。ゼンマイのエネルギーが一度に開放されるのを制御しつつ、そのエネルギーをテンプに与え規則正しい往復運動に変える働きをする。 脱進調速機脱進機構を使った調速機のこと。ゼンマイに蓄えられたエネルギーは輪列の介して動力となり、ガンギ車とアンクルからなる脱進機がそのエネルギーを往復運動に変換する。そして脱進機に接している調速機(テンプやヒゲゼンマイ)がエネルギーが一気に放出されるのを抑え、一定の往復運動を保つ。その動力を再び脱進機に戻す。このような仕組みを脱進調速機と言う。 タフソーラーカシオが開発した、電池交換不要の腕時計用ソーラー発電システム。文字盤に搭載されたソーラーパネルが、光を受けて発電。内臓された大容量2次電池にそれを蓄えることで時計を駆動する構造になっている。太陽光はもちろん、蛍光灯などのわずかな光でも駆動に十分な力を発電することができ、 タフムーブメント世界6局の標準時刻電波に対応する「マルチバンド6」や「タフソーラー」機能の他、ムーブの破損事故を防止する「ハイブリッドマウント構造」、「針位置自動補正機能」などを装備したカシオの多機能ソーラー電波ムーブメント。 WPHH「フランク・ミュラー・ウォッチランド」グループが主催する新作展示発表会。フランク・ミュラーを中心とし、ピエール・クンツやマーティン・ブラウンなどが参加。ジュネーブ公害・レマン湖畔にあるグループの本拠地「ウォッチランド」で毎年独自開催している。グループの新作やコンセプトウォッチなどがマスコミや業界関係者、VIP向けに披露されている。 ダボ日付を早送りするためのプッシュボタンのこと。 短針時を示す針、すなわち時計のこと。分を示す分針(長針)と比べ短いのでこう呼ばれる。 地板ムーブメントの土台となる金属盤。あらかじめ穴や凹みが作成されており、それに合わせて歯車やネジなど部品が組み立てられるようになっている。穴や凹みの位置は、ムーブメントの種類サイズによって異なり、通常はキャリバー別に設計&製造されている。ちなみにムーブメントのサイズや型などは、この地板のサイズで表記されるのが一般的だ。 GMTウォッチ時計とは別に24時間で1周する24時間針や、12~24時間表記のベゼル(インナーリング)などを用いることで、同時に2カ国以上の現在時刻を表示するこおができる機能を持つ時計。 チタンカーバイドガス化したチタンを高温で金属表面に付着させたカーボンと反応させることにより、強固な炭化皮膜を形成する加工技術。 蓄光塗料太陽光や人工光など光のエネルギーを蓄え、暗闇でそのエネルギーを放出し光らせる素材。針や目盛りに使われる。現在では放射性物質を含まないN夜光などの光を蓄積するタイプの塗料を使用しているが、以前は放射性物質のトリチウムやラジウムなど、自然発光するものを使用していた。 中留ベルトやブレスレットの留め部分のことで、素材もデザインも様々。スライドタイプやプッシュ式、プレートを3枚使った三つ折タイプなど着脱方法も色々ある。バックルとも言う。 長針分針のこと。ダイバーズウォッチでは長針を読み誤らないようにするため、認識しやすいデザインになっている。 調速機ゼンマイの動力を瞬時に放出させないように速度を一定に保ち、その動力を再び脱進機に戻す機構。テンプやヒゲゼンマイから成る。 直進式脱進機1715年にイギリス人のジョージ・グラハムが考案したアンクル脱進機で、ガンギ車からアンクル、振り石、天真まで直線状に配列されている。 チラネジテンプのバランスをとるために天輪に取り付けられた極小のネジのこと。テンプのバランスを取るための錘。テンプがアンバランスだと時計の姿勢によって進み、遅れの影響が出てくる。必要に応じて錘を加えたり、削って軽くする。取り付ける位置を変えて温度補正をすることもできる。 筒カナ長針が装着されているカナ。2番車と同軸上にあり、運針時は2番車と一緒に回転する。時刻合わせの時には筒カナの内側がすべり、独自に回転する仕組み。 車時刻を合わせるのに必要となる鼓状の部品。片方の端はキチ車と噛み合うようにノコギリの歯のように斜めの歯が付いていて、もう一方の歯は小鉄車と噛み合うように作られている。巻真が通っている部分は角穴になっていて、巻真と一緒に回転する仕組みになっている。普段はキチ車と噛み合っているがリュウズを引くと、オシドリとカンヌキの働きによってキチ車から離され、時刻を合わせる小鉄車に連結させる。 爪石アンクル脱進機におけるアンクルのアーム部分に付いた石のこと。角度の異なる入りヅメと出ヅメがあり、ガンギ車の歯と噛み合うことによってゼンマイのエネルギーを規則正しい運動に変えている。 DLC加工炭化水素ガスを真空中で分解、非結晶化した炭素を素材表面に堆積させて硬化膜を作る、時計ケースやブレスの表面加工技術。その名の通り、ダイヤモンドに次ぐほどの高硬度を誇り、当初はゴルフのヘッドクラブの加工にも用いられていたほど。2000年頃から、その頑強性が着目され、シチズンが世界に先駆けて時計ケースやブレスの加工に応用している。 低振動テンプが振動する回数が少ない状態のことで、1時間に2万1600振動以下のものを低振動と言う。 デイトジャストロレックスが開発した機構で、24時ちょうどになると日付が変わる。またこの機構を搭載したモデルのことを言う。 デイト表示日付表示のことを指す。日付と曜日を表示するものをデイデイトと言い、24時ちょうどになると日付が変わる機構をデイトジャストと言う。両方ともロレックスが開発したもの。 ディフュージョンモデル高級なモデルに比べて低価格に設定された普及版のモデルのこと。ちなみにディフュージョンメーカーとは同メーカー内の製品のうち普及品のみで構成されたブランドのことを言う。ロレックスのディフュージョンブランドとしてつくられたチュードルは、当時ロレックスの半額以下の値で売られていた。 デジタルカウンタークロノグラフやストップウォッチに付いている1分間または1時間などの目盛の単位を100分割したもの。加算や減算を簡単に行なうことができる。 デジタルコンパス方位センサーを内臓するクオーツモデルで、ダイアル上に現れる液晶表示コンパスのこと。カシオの「プロトレック」などに搭載され、東西南北を示す2本の線が、あたかも針式のコンパスを見るように、画面上にリアルタイムで方角を表示するようになっている。 デタント脱進機イキリスの時計師ジョン・アーノルドが1780年頃に考案した脱進機構(正式にはスプリング・デタント脱進機という)。耐衝撃性に優れ、マリンクロノメーターなどの高精度デッキクロノックに主に採用されている。 デッドビートセコンド機械式時計は通常、流れるように滑らかな運針を見せるが、ガンギ車のバネなどに(1秒分の)力を蓄積することで、秒針を1秒ずつジャンプするように運針させる超複雑機構の一種。 手巻きムーブメントリューズの回転が専用歯車を伝って、最終的に香箱車を回すことでゼンマイを巻き上げる方式を採用したムーブメント。構造が比較的シンプルで、機械仕掛けらしい操作感が味わえるとファンも多い。 デュアルタイムウォッチメインの短針、長針とは別に文字盤内にもう一つ12時間計を設けることによって、2ヶ国の時刻を瞬時に読み取ることができる機能を持った時計のこと。メインの長針とは別にもう一本長針とは別にもう一本長針が付いたGMTモデルよりも、第2時刻が読み取りやすいのが特徴である。 デュボア・デプラマーセル・デプラによって1901年、ジュウ渓谷に創設されたムーブメント製造メーカー。クロノグラフやコンプリケーション・ムーブの開発&製造で知られ、1969年にはタグ・ホイヤーらと共に、世界初の自動巻きクロノグラフ・ムーブメント「クロノマチック」も開発している。 テレメーター光速と音速の差を測ることによって2点間の距離を割り出せる機能を持った目盛のこと、またはその目盛を搭載しているクロノグラフのことを言う。 テン真テンプの中心のこと。テン輪に取り付けられる軸部分のことで、先端の径は腕時計で0.08m/n前後。 天体時計太陽の位置、日の出、日の入りの時間、星雲星団などの表示、恒星の位置など天体の情報を計測、表示できる機能を持った時計のこと。 電波時計誤差が10万年に1秒しか生じない超高精度な原子時計で制御された標準時刻電波を、時計に内臓された受信アンテナで自動受信。もし誤差があった場合、それを自動的に修正する機能を持った時計。1990年にドイツのユンハンスが世界で初めて製品化に成功。日本ではシチズンが1993年に開発に成功している。 テンプテン輪やテン真、振り座などで構成された調速を行なう部分。輪列、ガンギ車、アンクルと伝わってきた主ゼンマイの動力を、テンプの中心にあるヒゲゼンマイと共に規則正しい速度に変換する働きをしている。現在使われている主なテンプはチラネジ付きとチラネジなしの2種類。テンプを保持する受けのことをテンプ受けと言う。 等時性「往復運動をしている振り子は、振り幅が大きくても小さくても一往復する時間は変わらない」というイタリアの天文・物理学者ガリレオが発見した性質。 トゥールビヨンアブラアン・ルイ・ブレゲが1795年に発明した複雑機構。地球には重力があるためその重力によって、時計には姿勢差が生じてくる。その姿勢差を相殺するための機能。振動するテンプと脱進機を収めたキャリッジと呼ばれる籠が回転することによって、重力の影響を平均化する仕組みになっている。トゥールビヨンとはフランス語で「渦巻き」という意味。 ドクターズウォッチ秒針が長針、短針を持つ文字盤から独立していて、文字盤の半分ほどの割合を占めている時計のこと。医者や看護婦が患者の脈を測るために秒針が短針や長針で隠れないようにするために考案された。 トノーケース樽型のケースのことでカジュアルな印象をもたらす。レディスモデルに多かったデザインだが、1920~30年代にかけて、角型のムーブメントの開発が困難だった時代に、丸型ムーブメントを使用しながら角型に近づけるために考案された。 ドーム形風防ドーム形に盛り上がった風防のことで、サファイアガラスをドーム形にするには高い技術力が必要となる。 ドライバーズウォッチ車を運転してハンドルを握ったままの状態でも、ハンドルから腕を放さずに時刻が読み取りやすいよう、ダイアル全体を傾けた構造にしてある時計。 ドライビングホイール4番車と連動して1分間で1回転しているクロノグラフ機構特有の歯車。スタートボタンを押すとトランスミッションホイールがクロノグラフランナーと噛み合い、動力を伝える役割をする。 トリプルカレンダー月・日・曜日・月齢(ムーンフェイズ)を表示することができるカレンダー機能のこと。小窓で表示するタイプが多いが、針で文字盤の目盛を示すポンターデイト表示のものなどもある。 |
用語集【な~ほ】 |
中3針時・分・行の針が、3本ともダイアルセンター軸にセットされた時計の総称.視認性に優れ、ダイアルデザインもシンプルにまとめやすいため、現在のアナログ式モデルではもっとも広く採用されている。 NASA時計テスト1962年より始まったアポロ計画で、公式クロノグラフを選ぶために設けられたテスト。衝撃や高気圧、急激な温度変化など、11項目にわたるテストに合格したのがオメガのスピードマスターだった。 ナースウォッチ看護婦向けに作られた時計で、清潔感を保つことができて作業がしやすいように、ピンやクリップなどで服に留められるようになっている。また見誤ることがないように、文字盤の色やインデックスが見やすいようなデザインになっている。 ナビゲーションウォッチ目的地までの到達時間、距離、移動速度などを算出することができる航海や飛行に適した機能を持つ時計。その多くはクロノグラフを搭載している。 24時間ベゼル1~24の数値が描かれたベゼル。GMTウォッチなどに主に装備され、たとえば時針(短針)をダイアル上のインデックスに合わせてホームタイムを表示、GMT針をベゼル上の1~24に合わせてセカンドタイムを表示させるなど、同時に2カ国以上の時刻帯を表示させる際に使用する。 日常生活防水洗顔をしたときに跳ねる水滴や雨や汗など、日常生活においての水分に耐えられる程度の防水性能のこと。通常は、3気圧(30m)の防水となっている。その検査方法などはJISによって規定されている。 日差1日の時計の進み、遅れ度合いを数字で表したもの。ムーブメントの性能や気候、湿度、季節などによって日差は異なってくる。 2番カナ2番車の真軸まわりに付いている歯車で、香箱と噛み合い2番車に動力を伝える役割をしている。 2番車分針と同軸にある歯車で、香箱からの動力を増速されて3番車へと伝える。ムーブメントの中央に配置され、1時間に1回転する。 ねじ込み式リューズ湿気や水分の侵入を防ぐため、ネジ式構造にしたリューズのこと。ネジを根本までしっかり閉めこむことで機密性を確保できる。ちなみに、1926年にロレックスが開発した世界初の完全防水時計ケース「オイスターケース」に採用されたネジ込み式リューズが、その源流とされている。 年差1年間の時計の進み、遅れ度合いを数字で表したもの。機械式時計の平均年差は約2時間である ハイビート時計の精度や安定性を向上させるため、テンプの振動数(ビート)を毎秒8回(毎時2万8800回)以上に設計したムーブメントのこと。小型で軽量のテンプを採用し、強力なヒゲゼンマイを装備することでテンプを高速振動させる構造になっており、一般的にはロービート(毎秒6振動=毎時2万1600振動以下)タイプのムーブよりテンプの作動安定性に優れ(多少の姿勢差やショックに動じない)、時計をより高精度に調整可能となっている。 バイメタルテンプ種類の異なる2つの金属を張り合わせて作ったテンプのこと。ヒゲの弾性率の変化を補正するために、温度変化によって生じる影響の受け方が異なる2種類の金属を組み合わせて使う。 パイロットウォッチ強烈な日差しやGに見舞われる航空機のコックピット内でも確かに作動し、どんな状況下でも時刻を確実に読み取れるよう独自の工夫が盛り込まれた、パイロット用モデルの総称。 バーゼルフェアスイスのバーゼルで毎年春に行なわれる世界最大の時計・宝飾品の国際見本市。14世紀から続いていたスイス工業展に時計メーカーが参加したのが始まりで、1983年に時計・宝飾品部門が独立して今の形となった。 ハック機構時刻合わせを秒単位で正確に行なえるよう、リューズを引くと秒針が止まる機能。 パテックフィリップ・シール2009年からパテック フィリップが採用した新たな品質基準規格。クロノメーターを超える高精度さや高品質性、耐久性、審美性、アフターサービス体制などを総合的に厳格に審査。すべての面で「最高峰」と認定された際にのみ発行される。 ハートカムクロノグラフランナーやミニッツレコーディングホイール、アワーレコーディングランナーに付いているハート形のパーツ。リセット用のハンマーがハートカムを叩くと、クロノグラフのストップウォッチがリセットされる。 ハニーゴールドその名の通り、蜂蜜のような深みと艶と輝きを持ったゴールドカラーのこと。 バネ棒ケースとベルトやブレスレットを固定するための棒状の部品。内部に伸縮するバネが入っており、エンドピース穴へ差し込みやすい仕組みになっている。ベルト交換などでバネ棒を外す時に使う道具をバネ棒外しと言う。 ハーフハンターケース蓋の中央に丸く開いた窓があり、蓋を開けずに時間が読み取れるようになったケース。フランスの皇帝ナポレオンが考案したとされているため、ナポレオンケースとも呼ばれたり、デミハンターやハーフサボネットとも呼ばれる。 パーペチュアルロレックス社が開発した、世界初の360度回転式ローターを搭載した自動巻き機構のこと(1933年に同社がパテントを取得)。 パーペチュアルカレンダー西暦2100年まで無調整で閏年も自動的に表示するカレンダー機構。普通のデイト表示などは2月28日や4月、6月、9月、11月など30日までの月の場合、表示を修正しなければならない。しかし、パーペチュアルカレンダーは4年に一度の閏年もプログラムされた歯車を持つので修正不要である。 パラクローム製ヒゲゼンマイニオブ(Ni)をメインとしたナフニウウム(Hf)との合金であるパラクロームを材質に採用した特殊なヒゲゼンマイ。耐磁性に優れ、湿度変化にも強い性質を持つため、精度の維持と安定化に高い効果を発揮する。 パラシュートテンプの軸受けに窪みを設けた宝石をセットし、バネで支えられた土台に載せることで、時計が衝撃を受けた際にもその精度や作動を安定させるための装置。アブラアン・ルイ・ブレゲが1790年に考案した、耐衝撃機構のルーツともいえる装置。 針時針、分針、秒針などの文字盤上の時刻や数字を示す針状のパーツ。指針とも言う。種類としては先端に輪の付いたブレゲ針、中が肉抜きされたスケルトン針、葉っぱの形をしたリーフ、鉛筆の形をしたペンシル、時針部分にメルセデスベンツのロゴに似た形をしているベンツ、その他ドーフィン、アルファ、アプライト・ラインなど様々な種類がある。 バルジュー1901年にスイスで創業したムエボーシュメーカーで、特にクロノグラフのムーブメントに関して高い評価を受けていた。傑作クロノグラフムーブメントキャリバー23などを作り出し、様々な時計会社に供給された。1983年にETA社に統合されたがそのムーブメントの造形は美術品の域に達し、最高級時計の心臓として動き続けている。 パルスメーターゼンマイの巻上げがあとどの位残っているかを表示できる機能。残量を表示するインダイヤルをパワーリサーブ・インジケーターと言う。 パルソマチック世界初のLEDウォッチ「パルサー」の誕生40周年を記念して、2010年バーゼルワールドで発表されたハミルトンの新作モデル。自動巻きロータ-で発生した機械エネルギーを、マイクロジェネレーターによって電気エネルギーに変換。高性能な蓄電装置によりLCDディスプレイにデジタル表示する機構を搭載する。 バレッツアンクルの先に装備される、人工ルビーなどのツメ石のこと。 バレルゼンマイが収納されている円筒状の部品。日本の時計業界では香箱とも呼ばれる。 パワーリザーブその都営が、ゼンマイをフルに巻き上げた状態から、ゼンマイが緩んで停止してしまうまでの、おおよそその時間。 パワーリザーブ・インジケーターゼンマイの巻上げ残量を、ダイアル上に針や数値で表示する装置。アブラアン・ルイ・ブレゲが1780年代の自動巻きモデル(懐中時計)に搭載したのが、その源流といわれている。 半回転一方向巻き上げ式自動巻自動巻きのローターが左右約90度の範囲で動く構造のことを半回転と言い、ローターが一方向に動いた時だけゼンマイが巻き上がる仕組みのことを言う。ムーブメントを薄くすることができるが、ローターが90度しか動かないため、巻き上げ効率が悪い。初期の自動巻ムーブメントによく見られる。オメガなどの3/4回転のローターもハーフローターと呼んでいる。 ハンターケース文字盤側とケース裏側に蓋が付いたケースで、文字盤を完全に覆うフルハンターと中心に窓があり、開かなくても時間を読みとれるハーフハンターなどがある。ハンティングケースやサボネットとも呼ばれる。 反転ケース風防を保護するために考案されたケースで、ムーブメントを納めた部分を裏返すことができる。ジャガー・ルクルト社のレベルソが有名である。 ハンド時計の針の海外での名称。針が重いとぜんまいの力(トルク)が余分にかかりパワーリザーブが低下するだけでなく、軸列機構などにも大きな負荷が生じるため、腕時計の場合は可能な限り軽い素材で薄く成型されている。そのデザインや形状にはさまざまなタイプがあり、それぞれアロー(矢印)、バトン(棒)、リーフ(葉)、バー(細い棒)、ペンシル(鉛筆)などの名称が付けられている。 バンド時計を腕に付けるためのベルトのことで、主に革やウレタン素材などが使われる、金属製のベルトはブレスレットとよび、バンドとは区別して使われることが多い。 ハンマークロノグラフ機構のリセットボタンに接続するレバーのこと。クロノグラフのリセットボタンを押すとハートカムがハンマーに叩かれ、積算計の針がゼロに戻る仕組みになっている。ミニッツリピーターの場合は鐘を叩くレバーアームのことを指す。 ハンマースプリングクロノグラフでスタート、ストップ、リセットを押したときに、ハンマーの動きを制御するスプリングレバーのこと。 P.999/1パネライが2010年SIHHで発表した、インハウス・手巻きムーブメント。直径12リーニュ(27.4㎜)、厚さ3㎜と、従来ムーブに比べてスリムでコンパクトなサイズが特徴(ムーブ厚はP.9000の半分以下)。同社製の手巻き最新コレクション「ラジオミール チタニオ 42㎜」などに搭載されている。 ヒゲゼンマイテンプに取り付けられた細かいヒゲ状のゼンマイのこと。輪列を通りガンギ車からアンクルの衝撃を介して伝えられたエネルギーを天輪の振動に変える役割をしている。 ヒゲ持ちヒゲゼンマイとテンプ受けを繋ぐパーツで、ヒゲゼンマイの外側に付属する PG赤みのある金、ピンクゴールドの略で金75%、銀、銅、パラジウム、亜鉛25%で作られている。YGはイエローゴールドで、WGはホワイトゴールド。Ptはプラチナで金よりも硬度が低く、加工が難しいため時計のケースには適していない。1960年代は金の3倍の価格であったため、高級時計に使われていた。 美錠(尾錠)革のベルトにおいて12時側と6時側のベルトを留める金具のことを言う。ベルトの穴に差し込む中央の棒のことをツク棒と言う。 ビックデイトダイアル内部に重なり合うように設置された2枚の専用ディスク盤(それぞれ十の位=10~30&31と、一の位=0~9の数値が描かれている)を使って、日付表示を行なう方式。通常のデイト表示より大きく、拡大レンズを装着しなくても鮮明に日付けを表示することができるが、機構は複雑なため主に高級時計に採用されている。 日時計紀元前4000年~3000年頃に古代エジプトで考案された古典的な時計で、柱や岩などある一定の形をしたものに日光が当たることによってできる影を計測して時刻を知る。 ビート振動数の項参照 PVD加工ケース「真空蒸着」「IP加工」「スパッタリング」の3種の方法のいずれかで、金属表面に薄い硬化膜を作る物理気相成長法の総称。メッキのような液に浸す湿式加工と異なり、蒸発させた金属原子を真空中で素材に噴き付け、表面に膜を形成させる乾式加工技法。分子レベルで密着しているのでメッキと異なり剥がれ難く、頑丈な表面加工ができる。 秒帰零秒針がゼロ位置に急速に戻る機能。クロノグラフやストップウォッチなどのリセットボタンを押したときにゼロに戻る。 標準時計時計職人が作った時計の時刻を合わせるために使用したり、天文台で天体観測お行なう際に使用した時計のこと。レギュレターとも言う。文字盤内に時、分、秒がそれぞれ個別に表示されている。クロノスイスやオーガスト・レイモンドなど限られたメーカーでしか製作することができなかった。 秒針秒数を示す針のこと。セコンド針とも言う。時計、分針と共にセンターに付いているものをセンターセコンド、インダイヤルにあるものをスモールセコンドと言う。 秒針規正秒単位まで合わせるため、リュウズを引くことによって一時的に秒針を止めることができる機能のこと。秒針停止とも言う。 平ヒゲ平らに巻かれたヒゲのこと。これに対してブレゲが発明した巻上げヒゲ(ブレゲヒゲ)がある。 ピラーホイールクロノグラフ機構の全機能を制御している重要なパーツで、スタートやリセットボタンを押すとこのピラーホイールが回転し、スタート、ストップ、リセットを行なう。 ピラーホイール式クロノグラフピラーホイールを使用したクロノグラフのこと。ピラーホイールの換わりにカムを作ったカム式クロノグラフに比べ製造が難しいため、コストも高くなる。 ヒンジ(蝶番)式ケースヒンジを使ってガラス縁と裏蓋をケース本体に固定しているケースのこと。1920年頃までのケースに多く見られる。 風防ガラスの項参照 風防フォーリンボール時計17世紀頃のヨーロッパに登場したユニークな球体時計。球体の周りには24時間で1周する文字盤が取り付けられていて、その下の人形が文字盤を指して時刻を知らせるという仕組み。 風防複雑時計コンプリケーションウォッチのことを言う。トゥールビヨンなど複雑機構が組み込まれた時計のこと。 プッシュボタンクロノグラフ機構をスタート、ストップ、リセットするためのボタンのこと。非防水は角ボタン、防水は丸ボタンのものが多い。積算機能が付いていないクロノグラフはボタンがひとつである。 フライバッククロノグラフにおいてストップウォッチ機能を使用中にリセットボタンを押すと、秒針が瞬時に戻って再び計測を始める機能。続けて計測をする場合に便利。 プラスチック風防アクリル樹脂製の風防のことで、生産コストが低く加工性と透過性に優れている。しかしその反面、傷が付きやすく変色することがある。 振り子時計1656年にオランダの天文・物理学者クリスチャン・ホイヘンスが開発した等時性を利用した時計。日差は10秒ほどであった。 ブリッジ歯車やテンプの真軸を支えるプレートで、部品を固定する役割をする。日本語では「受け」と呼ばれる。 フリップロックブレスクラスプ(留め金具)内側部分に、折りたたんだ上体の延長板を収納したタイプのブレスレットのこと。ウエットスーツや潜水服などを着用した際にも板を伸ばして長さを延長すれば、そのまま容易に装着できるようになっている。 プリントインデックスインデックスの加工方法のうち、最も一般的に用いられる手法。文字盤に直接、数値などをプリント加工する方式。 ブルガリ グループブルガリを総帥とするブランドグループ。2000年にジェラルド・ジェンタとダニエル・ロートを傘下に加えている。 ブルースチール高品質のスチールに焼き入れすることで、光沢感ある美しいブルーの酸化被膜をを作った銅のこと。美しいブルーの発色が難しく量産できないため、高級時計の針などに使用される。焼きを入れることによって錆びにくくなる。 ブレーキレバークロノグラフ機構において、ストップボタンを押したときにクロノグラフランナーの動きを抑え込むレバーのこと。 ブレゲヒゲヒゲゼンマイの一種でアブラアン・ルイ・ブレゲが考案したもの。内側に巻き上げられた部分より、ヒゲの外側を上に持ち上げた螺旋状のヒゲ。平ヒゲに比べて偏芯運動が少ないため、等時性と精度が高まる。しかし、製作が難しく時計の厚みが増してしまうというマイナス面もある。 ブレスレット金属製のバンドのことで、パイプやピン、コマ、バックルなどで構成されている。コマが3連、5連と増えていくことによって、より華やかになる。 プロダクションカウンティング1時間当たりの生産個数を計測することができる工業生産用のクロノグラフ。速度計測と同様にタキメーターを使い、製品1つを作るのにかかる時間を計測する。ストップしたときにクロノグラフ針が指す数が1時間当たりの生産個数となる。 ヘアスプリングヒゲゼンマイのこと。テンプの動きを制御すると共に、その動力源ともなる部品。 ヘアライン仕上げステンレススチールのケースや裏蓋、ブレスレットなどに髪の毛のような細かいラインを施したもの。ブラシなどで摺って加工している。 ベースムーブムーブ(エボシュ)メーカーなどから仕入れられた、みかんセの機械のこと。時計メーカーは仕入れたエボシュを分解し、パーツのリファインや調整、装飾加工などを経て完成品に仕上げるのが一般的なので、完成品に対してその基本(ベース)となったムーブメントという意味でこう呼ばれている。 ベゼル風防を固定するために付けられたリングのこと。プラスチックは金属のベゼルの上に付ける。エンジンのようなデザインをしたエンジンターンドやギザギザのピラミッドベゼル、段差が付いたステップドなどの種類がある。また、ダイバーズウォッチなどに付いている経過時間を計れるものを回転ベゼルと言う。 (ヘリウム)ガス・エスケープバルブ飽和潜水を行なう際、ダイバーが腕に着けた時計内には分子の小さいヘリウムガスが侵入してしまうもの。浮上時に水圧が低くなると、自然に抜け切れなかったそのガスが膨張してケース内圧を高め、ガラスなどを破損してしまう恐れがあるため、そのガス抜きを行なうための装置。 ペリフェラルローター通常は半円形部品をセンター軸に固定する自動巻きローターを、ペリフェラル(=周囲の)という言葉のようにムーブ外周部に設置されたリング状部品に替えた画期的な自動巻き装置。カール・F・ブレラが開発したオリジナル機構。 ベルト腕時計を腕に付けるためのベルトのこと。皮ベルトなどは小穴にツク棒を差し込んで固定するタイプが主流だが、中留が付いたものなどもある。主な素材は、カーフ(生後6ヶ月以内の子牛皮)、オーストリッチ(ダチョウの皮)、ワニ皮(クロコダイルやケイマン)、ピッグスキン(ブタ皮)、バッファロー(水牛の皮)、シャーク(サメ皮)、リザード(トカゲ)、コブラ、合成皮革、ウレタンなどがある。一般的に金属製のものをブレスレットと呼ぶ。 ペルラージュ装飾熟練職人が専用の施盤機で刻む、細かな渦巻き模様(一説には「真珠をイメージした模様」ともいわれる)。 ペンデュラム・コンセプトタグ・ホイヤーが2010年のバーゼルワールドで発表したコンセプトウォッチ。従来のヒゲゼンマイの代わりに、磁石を利用した「仮想スプリング」を採用した画期的モデル。「磁力」を応用することでヒゲゼンマイの物理的限界や弱点を克服し、毎時4万3200振動の高速回転型テンプを実現している。 ポインターデイトダイアル周囲に描かれた1~31の数値を、1ヶ月で1周するカレンダー専用針が指し示すことで日付を表示する方式。 防水性能ウォータープルーフの項参照 飽和潜水用防水不活性ガスと酸素を混ぜた高圧混合ガスを用いるダイビングにおいて最低200m以上の潜水に耐えられる性能のこと。深海での高圧に慣れるため、ヘリウムなどの不活性ガスが混合されたガスを吸って加圧し、身体を飽和させた状態にして潜水を行なう。時計にもそのような過酷な水圧にも耐えられる性能が必要とされる。混合ガス潜水用防水とも言う。 歩度日差、月差、年差の総称で時計の進み具合や遅れ具合のこと。歩度緩急とはこの歩度を調整することを言い、機械式はヒゲゼンマイに付いている緩急針を操作することによって歩度を調整する。 ポリッシュ仕上げ鏡面仕上げのことで、車などでも使われることが多い。鏡のような光沢で高級感溢れる仕上がりとなる。 ホールマーク金や銀の純度はユーザーが見ただけでは簡単には確認できないため、国や公的検査機関などがあらかじめその純度を検査。法廷基準を満たしたと認められた場合に刻印される品質保証マーク。 |